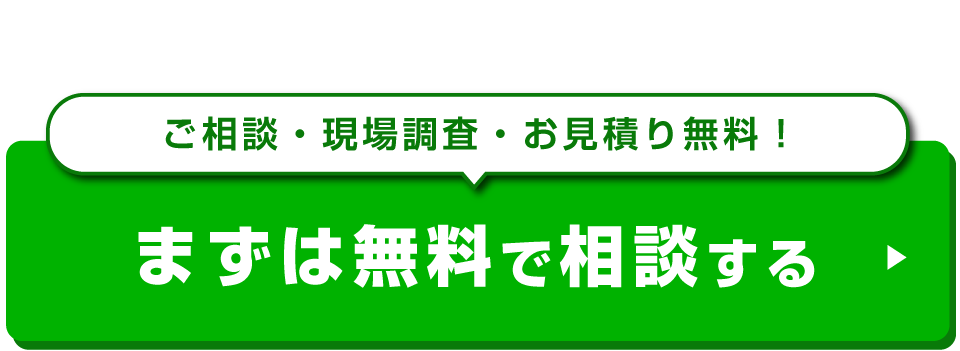目次
ドッグラン用板塀・ウッドフェンス完全ガイド|愛犬の安全を守る選び方から施工まで徹底解説
愛犬が庭で安全に遊べる空間を作りたい。そんな想いを持つ飼い主さんの多くが直面するのが「どんなフェンスを設置すれば安心か」という問題です。
ドッグランに適したフェンスは「脱走を防ぐ高さ」「犬の安全を確保する構造」「見た目と耐久性のバランス」の3つが欠かせません。中でもウッドフェンス(板塀)は、見た目の自然さと柔らかさで人気が高く、人工素材では得られない温もりを持っています。
この記事では、犬の行動特性や体格を踏まえた上で、フェンスの高さ・木材・板の間隔・施工方法など、ドッグランを安全に運用するための実践的な知識を詳しく紹介します。
なぜドッグランにウッドフェンスが最適なのか
ウッドフェンスは、犬の安全を守りながら庭全体のデザイン性も高められる理想的な選択肢です。金属製フェンスやメッシュフェンスと比べて、木材は自然素材のため犬がぶつかってもケガをしにくく、温度変化にも比較的穏やかに対応します。
また、ウッドフェンスは通気性・視認性・遮蔽性のバランスを自由に設計できるのが大きなメリットです。完全な目隠しではなく、板の間隔を適度に設けることで、風通しを確保しつつ圧迫感を減らせます。
ウッドフェンスが選ばれる7つの理由
- 1. 脱走防止性能が高い
犬の体高と跳躍力を考慮した高さ設計が可能で、隙間からのすり抜けも防げます。 - 2. 犬にやさしい素材
天然木のため、金属よりも衝撃吸収性があり、犬がぶつかってもケガをしにくい。 - 3. 見た目が美しい
庭の景観に自然に馴染み、住宅外観との統一感を出せます。 - 4. カスタマイズ性が高い
犬種や性格に応じて、高さや板間隔を自由に調整できます。 - 5. メンテナンス性が良い
部分的な補修や板の交換が容易で、長期間利用可能。 - 6. 遮蔽効果と風通しを両立
プライバシーを保ちつつ、閉塞感を減らす設計が可能。 - 7. DIYにも向いている
木材加工がしやすく、自作でも施工可能。
こうした理由から、ドッグランにウッドフェンスを採用する家庭や施設は年々増えています。特に「見た目の温もり」と「安全性」を両立したい方には最適な素材といえるでしょう。
犬種別・体格別の必要なフェンス高さ
フェンス設計で最も重要なのは「高さ」です。犬は想像以上にジャンプ力があり、見た目以上の高さを跳び越えることがあります。体格や運動能力に合わせて最適な高さを設定することが脱走防止の基本です。
小型犬(体重10kg以下)
代表的な犬種: トイプードル、チワワ、ポメラニアン、ミニチュアダックスなど。
推奨高さ: 120〜150cm。
小型犬でも体高の2倍近いジャンプをすることがあります。ステップや家具などが近くにあると、それを足場にさらに高く跳べるため、最低でも120cm、できれば150cmを確保するのが理想です。
中型犬(体重10〜25kg)
代表的な犬種: 柴犬、ビーグル、ボーダーコリー、ウェルシュコーギーなど。
推奨高さ: 150〜180cm。
中型犬はジャンプ力が高く、フェンスに前脚をかけて登ろうとする個体も多いです。特に運動能力の高い犬種では、180cm程度の高さを推奨します。
大型犬(体重25kg以上)
代表的な犬種: ゴールデンレトリバー、ラブラドール、シベリアンハスキー、ジャーマンシェパードなど。
推奨高さ: 180〜200cm。
大型犬はジャンプ力だけでなく体重も大きいため、フェンスの強度自体が重要になります。高さだけでなく、支柱の間隔・基礎の固定・風への耐久性も十分に考慮しましょう。
運動能力の高い犬種への注意
ボーダーコリーやハスキーなど、運動能力が高い犬種は標準よりも30cm高く設定するのがおすすめです。また、フェンス付近に足場になるもの(ベンチ・植木鉢・物置など)を置かないことも脱走防止につながります。
犬が脱走するケースの多くは、「飼い主の想定を超える動き」をしたときに起こります。フェンスの高さは“ギリギリ”ではなく“余裕を持って”設計するのが鉄則です。
デザイン選びのポイント|安全性と景観の両立
ウッドフェンスは、単に脱走を防ぐだけでなく、庭全体の印象を左右する大きな要素です。デザインを選ぶ際は、「安全性」「視認性」「通気性」「メンテナンス性」の4つを軸に検討しましょう。
1. 横板フェンス(横張り)
横方向に板を張るタイプで、モダンな印象になります。板の間隔を細かく調整でき、目隠し効果も高いのが特徴です。
犬の安全を考える場合、板の間隔を狭くすることで頭や足が挟まるリスクを軽減できます。ただし、風通しを確保するために、板の隙間を5〜10mm程度に保つとバランスが取れます。
2. 縦板フェンス(縦張り)
縦方向に板を張るタイプで、ナチュラルな印象を与えます。犬がよじ登りにくく、脱走防止性能が高いのが特徴です。特に運動能力の高い犬種には縦板タイプがおすすめです。
ただし、板の反り防止のために裏桟(うらざん)を確実に入れ、固定強度を上げておくことが重要です。
3. 目隠しフェンス(完全遮蔽タイプ)
完全なプライバシー確保を目的としたフェンスです。道路や隣家との距離が近い場合に有効ですが、犬にとっては外の刺激が減る分、ストレスが溜まりやすくなることもあります。
犬が外の様子を見られないことで不安を感じる場合は、部分的に透過部(スリットや小窓)を設けると良いでしょう。
4. 半目隠しフェンス
上部を開放し、下部だけ板を密に張るタイプです。外からの視線をある程度遮りつつ、圧迫感を減らすことができます。風通しや日当たりも確保でき、庭の植栽との相性も良好です。
5. 格子フェンス(ルーバータイプ)
斜めに板を取り付け、外からの視線を遮りつつ風を通すデザインです。スタイリッシュでモダンな印象を与えますが、犬が小型の場合は隙間から顔を出さないよう注意が必要です。
6. 組み合わせデザイン
敷地の条件によっては、複数のフェンスデザインを組み合わせるのもおすすめです。たとえば、道路側は目隠しフェンス、庭側は通風重視の縦板フェンスにするなど、機能性とデザイン性を両立させましょう。
デザインを決める際は、犬がどのように遊ぶか、飼い主がどこから見守るかを考慮してレイアウトを設計することが重要です。
ドッグランに適した木材の選び方|犬に安全で長持ちする素材
ウッドフェンスの寿命や安全性を大きく左右するのが、木材の種類です。屋外で長期間使用するため、耐久性・防腐性・安全性の3つを重視して選ぶ必要があります。
1. 杉(スギ)
日本で最も一般的に使われる木材で、加工がしやすくコストも比較的安価です。見た目の美しさと軽さが特徴ですが、耐久性は高くないため、防腐処理が必須です。定期的なメンテナンスを前提にするなら、十分に実用的です。
2. レッドシダー(米杉)
天然の防腐・防虫成分を含み、屋外利用に非常に適しています。軽くて加工しやすく、香りも良い人気の木材です。色味が美しく、経年でシルバーグレーに変化するため、自然な風合いを楽しみたい方におすすめです。
3. イペ・ウリン(ハードウッド)
非常に高い耐久性を誇る高級木材で、公共施設やデッキでも採用されます。15〜20年は持つとされ、メンテナンス頻度も少なく済みます。ただし非常に硬いため、加工に専門工具が必要です。
4. アカシア・セランガンバツなど
ハードウッドの中でも比較的手頃な価格で入手可能な木材です。雨や紫外線にも強く、長期使用に適しています。油分を多く含むため、撥水性が高くカビにくいのが特徴です。
5. 防腐処理材(ACQ、加圧注入材)
安価な木材に防腐薬剤を加圧注入したもので、コストを抑えながら耐久性を確保できます。ただし、犬が噛む可能性のある部分には使用を避け、直接口に入らない高さで施工することが望ましいです。
6. 人工木(樹脂木)との比較
人工木(ウッドデッキなどに使われる樹脂+木粉素材)は、メンテナンス性は高いものの、犬が噛んだ際に樹脂片を誤飲するリスクがあります。見た目の自然さも天然木に劣るため、ドッグラン用途では天然木を推奨します。
木材を選ぶ際は、「安全性」「耐久性」「メンテナンス性」のバランスを考慮し、犬の行動範囲と性格に合ったものを選びましょう。
板の間隔設定と安全性|犬のサイズ・性格に合わせた最適設計
ウッドフェンスの板と板の間隔は、犬の安全性に直結する重要な要素です。間隔が広すぎると頭や足が挟まる危険があり、逆に狭すぎると通気性が悪くなり、湿気による劣化が早まります。
犬の大きさ別のおすすめ間隔
- 小型犬: 10〜15mm(指一本入る程度)
- 中型犬: 15〜20mm(指二本が入る程度)
- 大型犬: 20〜25mm(犬の鼻先が通らない程度)
フェンスの板間隔は、犬が頭や鼻を差し込んで外の様子を見ようとすることを考慮して設計しましょう。特に外部刺激に反応しやすい犬は、隙間から顔を出すことで興奮し、脱走や怪我のリスクが高まります。
安全性を高める設計のコツ
- 板間隔を均一に保つことで美観と構造強度を確保する。
- フェンスの下部に隙間を作らない(掘り返しによる脱走防止)。
- フェンス内側に犬が登れないよう、段差や足場を置かない。
- 高さ180cm以上の場合、上部に「返し(内傾斜)」を付けるとより安全。
特に柴犬やハスキーのように掘る習性がある犬の場合は、フェンス下部を30cm程度地中に埋め込むか、防草シートとブロックで補強すると安心です。
DIYでの施工方法|自分の手でつくるドッグランフェンス
ウッドフェンスは、基本的な道具と正しい手順を踏めばDIYでも十分に施工可能です。以下は、一般的なDIY施工の流れです。
必要な道具と材料
- 木材(板材・支柱)
- コンクリートブロックまたはモルタル
- 水平器・メジャー・電動ドリル・丸ノコ
- 屋外用ビス・ステンレス釘
- 防腐塗料・刷毛
- スコップ・軍手・脚立
施工手順
- ① 位置決めと地面の整地
フェンスの位置をロープでマーキングし、地面の凹凸を整えます。 - ② 支柱の設置
90cm〜100cm間隔で穴を掘り、支柱を垂直に立ててモルタルで固定します。最低でも地中に30cm埋めるのが目安です。 - ③ 板の取り付け
水平を保ちながら板を一枚ずつビス留めします。板間隔を均一にするため、スペーサーを使うと便利です。 - ④ 防腐塗装
屋外用の木材保護塗料を2回以上塗布します。犬が噛む恐れのある部分は、自然素材由来の塗料を選ぶと安心です。 - ⑤ 最終確認
全体の歪みやぐらつきを確認し、しっかり固定されていることを確認します。
DIYで施工する場合は、コストを抑えられる反面、水平・垂直の精度が甘いとフェンス全体が歪んでしまうリスクがあります。工具や作業環境に不安がある場合は、支柱の設置だけ専門業者に依頼する「部分施工」もおすすめです。
業者に依頼する場合のポイント
DIYが難しい場合や、長期的な耐久性を重視する場合は、専門業者に依頼するのが安心です。プロに依頼することで、地盤調整・水平施工・強度計算などを的確に行ってもらえます。
業者選びで確認すべきポイント
- ① 犬を飼っている施主への施工実績があるか
ドッグラン施工経験がある業者は、犬の行動や安全性への理解が深いです。 - ② 木材の品質と防腐処理方法
使用木材の種類、含水率、防腐処理の方法を確認しましょう。 - ③ 支柱基礎の施工方法
単なる地中埋めではなく、コンクリート基礎を使うかどうかをチェック。 - ④ メンテナンス保証の有無
施工後に板の反り・割れが発生した場合の対応を確認。 - ⑤ 見積りの内訳
「材料費」「施工費」「防腐塗装費」「処分費」など、内訳が明確な業者を選びましょう。
施工費の目安としては、フェンス1mあたりで8,000〜15,000円(材工込み)程度。使用木材や地盤状況により変動します。
メンテナンスと耐久性|長く安全に使い続けるために
ウッドフェンスを長持ちさせるには、定期的な点検とメンテナンスが欠かせません。犬が毎日触れる場所だからこそ、衛生面と安全性の両方に配慮しましょう。
日常的に行うメンテナンス
- 汚れの除去: 犬の尿や泥は、時間が経つと木の表面に染み込むため、早めに水拭きしましょう。
- 破損の確認: 板の割れや釘の浮きを定期的に点検し、早めに補修します。
- 噛み跡の点検: 犬が噛んで削れた部分はトゲが出ることがあるため、軽くサンドペーパーで磨いておくと安心です。
年1〜2回行うメンテナンス
- ① 再塗装
屋外用防腐塗料を1〜2年に1回塗り直すことで、紫外線や雨水から木材を保護します。 - ② ボルト・ビスの増し締め
湿気や乾燥によって木材が収縮すると、ビスが緩むことがあります。定期的に締め直すとフェンス全体の強度が保てます。 - ③ 防草対策
フェンスの根元に雑草が生えると、湿気を保ち木材が腐りやすくなります。防草シートや砂利を敷いておくとメンテナンスが楽になります。
耐久性の目安は、無塗装の杉材で約5〜7年、防腐処理済み材で10年前後、ハードウッドで15〜20年です。メンテナンスを怠らなければ、それ以上長持ちさせることも可能です。
トラブル事例と対処法
ウッドフェンスを長期間使用していると、気候や犬の行動によってさまざまなトラブルが発生することがあります。代表的な例とその対処法を紹介します。
トラブル① 板の反り・割れ
原因:乾湿の差や紫外線による木材の収縮。
対策:反りが出た部分は早めに交換。塗装前にしっかり乾燥させ、防腐剤を浸透させることで予防できます。
トラブル② 犬がフェンスを噛む
原因:退屈やストレス、歯の違和感など。
対策:噛んでも安全な木材を選び、犬が頻繁に噛む部分には保護カバーを取り付けます。根本的には運動量や遊び時間を増やすことが有効です。
トラブル③ フェンス下からの掘り脱走
原因:地中の隙間や柔らかい土。
対策:フェンス下部を30cm程度埋めるか、防草シートとコンクリートブロックで補強します。掘る癖のある犬には、柵内に防止ネットを敷くのも効果的です。
トラブル④ 近隣からの苦情(吠え声・見た目)
原因:犬が外の刺激に反応して吠える、またはフェンスが高すぎて圧迫感を与える場合。
対策:視線が抜けるルーバータイプに変更、または植栽で自然な目隠しを作ると解決します。
よくある質問
Q1. 木材の防腐剤は犬に害はない?
犬が直接舐めたり噛んだりする部分には、天然由来の防腐塗料(蜜蝋・柿渋など)を使用するのがおすすめです。一般的な防腐剤でも乾燥後は揮発して安全になりますが、施工後1〜2日は犬を近づけないようにしましょう。
Q2. ウッドフェンスはどれくらいで交換が必要?
木材の種類や環境にもよりますが、定期的にメンテナンスしていれば10〜15年は十分使用可能です。ハードウッド材を使用すれば20年以上持つケースもあります。
Q3. フェンスの下に隙間があるけど問題ない?
犬が掘る習性を持っている場合は危険です。5cm以上の隙間があると、小型犬でも潜り抜ける可能性があります。地面との接地部はしっかり密閉しましょう。
Q4. 塗装は何色が人気?
ナチュラル系では「ウォルナット」「チーク」「オーク」が人気です。住宅外観に合わせて、建物の外壁とトーンを揃えると統一感が出ます。
Q5. 風の強い地域でも設置できる?
できますが、支柱の基礎を強化し、板の間隔を広めに取るのがポイントです。完全な目隠しフェンスより、通風性のあるルーバー構造の方が耐風性に優れます。
まとめ|愛犬の安全は飼い主の責任
ウッドフェンスは、愛犬が安全に遊べる空間をつくるための大切な要素です。犬の体格・性格・行動パターンに合わせた高さや板間隔を設定し、定期的にメンテナンスを行うことで、安心して長く使えるドッグランが実現します。
「デザイン性」「安全性」「耐久性」をすべて満たすには、設計段階から専門業者に相談するのが最も確実です。あなたと愛犬の暮らしに合った最適なフェンスを見つけてください。

黒柴の「そらお」と雑種「まめこ」のパパ。元市議会議員。議員時代に、犬猫殺処分ゼロに向けた市民活動に携わったご縁で、保護犬「そらお」に出会い一緒に暮らし始める。外でしかトイレが出来ないそらおの特性から、自宅にドッグランをつくる。その際、ドッグラン専門施工業者の見つけずらさを痛感し、ドッグランホームズを開業。日々、自宅にドッグランを作りたい人の相談に乗る傍ら、全国にいる愛犬家外構プランナーとのネットワークを構築している。